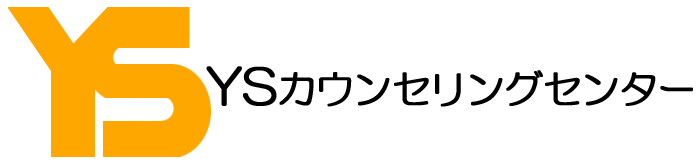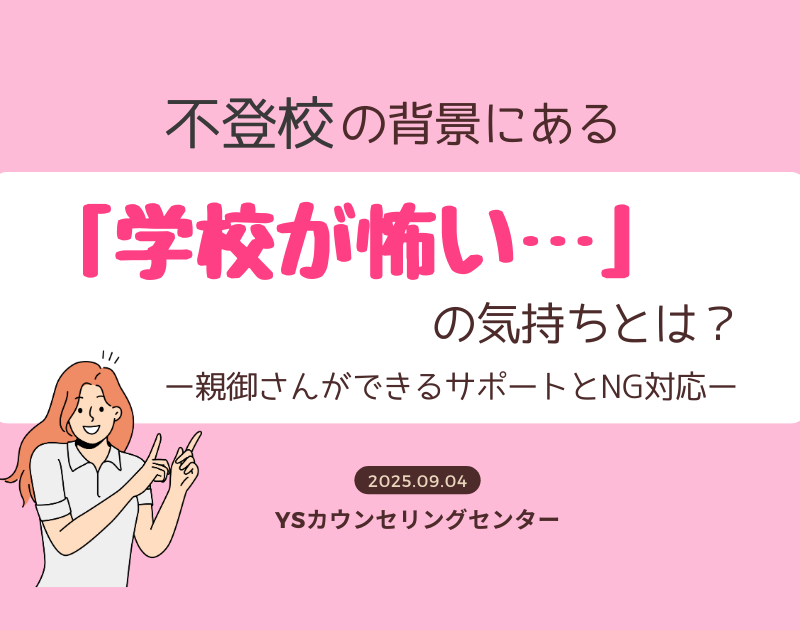この記事を書いた人:武山 円
YSカウンセリングセンターカウンセラー
スクールカウンセラー 公認心理師
不登校の背景にある「学校が怖い」気持ちとは?―親御さんができるサポートとNG対応
「学校が怖い」
「行きたくない」
と訴えるお子さんを前に、どう声をかけて悩んでしまうという
親御さんのお話をよくお聞きします。
「休ませて大丈夫なのだろうか」
「甘えているだけなのでは?」
と、不安や戸惑いを感じることもあるでしょう。
毎朝の登校をめぐるやりとりに、疲弊している親御さんも少なくありません。
実は「学校が怖い」と感じるのは珍しいことではなく、多くのお子さんが抱える心のSOSです。この記事では、その背景や理由、「学校が怖い」気持ちを和らげる方法、親御さんができる対応についてわかりやすく解説します。
愛するお子さんを理解する一助になりましたら幸いです。

この記事を読んでわかること
「学校が怖い…」と感じる理由と背景
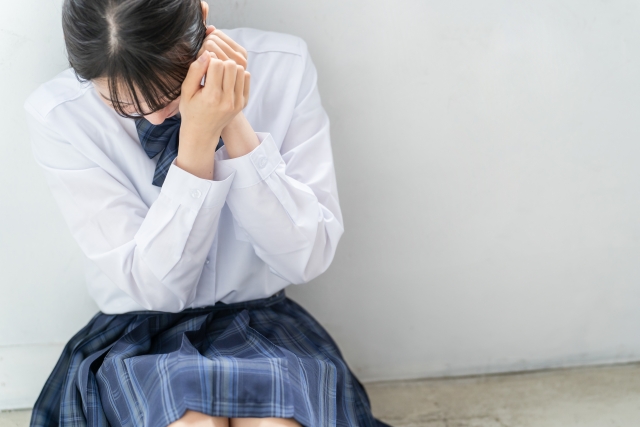
「学校に行きたくない」「学校が怖い」とお子さんが訴えると、親御さんは戸惑いや不安を抱くものです。「なぜ我が子だけがこんな思いを抱えているのだろう…」と思われるかもしれません。しかし、実際には、「学校が怖い」と感じている子どもたちは多く、不登校に「学校が怖い」という感情が大きく関わっているケースも少なくありません。では、なぜ子どもたちは学校を怖いと感じるのでしょうか。学校に対して「怖い」と感じる理由は、多くの場合、一つではありません。怖い理由を上手に言語化できない場合も多いです。「学校が怖い」理由を言えたとしても、それは表面的な理由にすぎず、それを取り除いたとしても、登校できないこともあります。ここでは、よくある理由をご紹介しますが、あくまで、目の前のお子さんを理解するうえでの参考としてご覧いただけたらと思います。
「学校が怖い」理由①人間関係の不安
まず多く見られるのが人間関係の不安です。いじめや仲間外れといった深刻な問題だけでなく、友達とのちょっとしたすれ違い、教室での孤独感も子どもにとっては大きな負担になります。学校生活の中心は人間関係であるため、安心できるつながりが持てないと「学校に行くこと自体が怖い」と感じてしまうのです。
「学校が怖い」理由②学習面での不安
学習面でのプレッシャーも大きな要因です。「授業についていけない」「発表ができない」「テストで点数がとれない」という気持ちは、子どもに強い劣等感を与えます。学習への苦手意識が強まると、「どうせまたできない」と、授業を考えるだけで学校が怖くなってしまいます。
「学校が怖い」理由③先生との関係
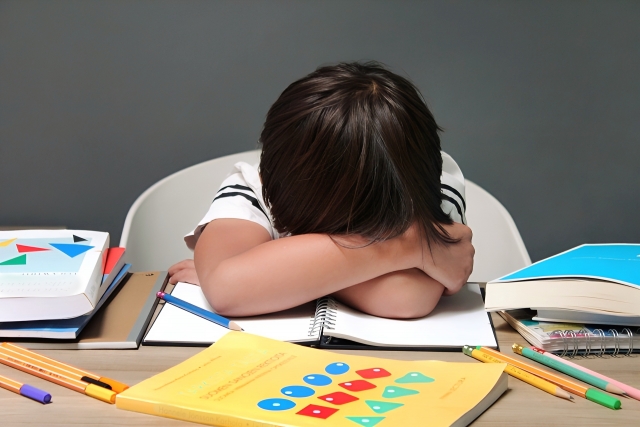
先生との関係が影響しているケースもあります。自分自身が厳しい指導を受けたというだけでなく、クラスメイトが怒られている場面を目にしたり、先生の様子を敏感に察知することで、学校への恐怖につながることもあります。「怒られてしまうでは」「先生に嫌われているのでは」などと感じることで心の緊張が高まり、教室で安心して過ごせなくなるのです。
「学校が怖い」理由④心身の不調や発達特性
さらに、心身の不調や発達特性が背景にあることもあります。たとえば、感受性が高く、不安を感じやすい性格のお子さんにとっては、集団生活を送るだけで心のエネルギーを消耗していて、特別な理由がなくても「学校が怖い」と感じることもあります。親御さんの仕事の変化や転居、ご家族の変化など、一見学校とは関係ないと思われるような変化によって、心が不安定になり、学校への恐怖感につながることもあります。
また、発達特性によって感覚過敏があったり、環境の変化に敏感なお子さんは、学校のざわざわした音や学校の日程の変化、先生の変化、突発的な出来事などにストレスを感じやすい傾向にあり、「学校が怖い」という気持ちの背景になっていることもあります。
いじめや人間関係のトラブルなどの特別な出来事が原因ではないケースも少なくありません。子どもたち自身も「なぜ怖いのかわからないけれど、行こうとすると体が動かない」と感じることもあります。「学校が怖い」理由は一つではなく、複数の要因が重なり合っていることが多いのです。「怖い」という気持ちは、単なるわがままや怠けではなく、お子さんにとって切実な心のサインであると理解していただけたらと思います。
また、発達特性によって感覚過敏があったり、環境の変化に敏感なお子さんは、学校のざわざわした音や学校の日程の変化、先生の変化、突発的な出来事などにストレスを感じやすい傾向にあり、「学校が怖い」という気持ちの背景になっていることもあります。
いじめや人間関係のトラブルなどの特別な出来事が原因ではないケースも少なくありません。子どもたち自身も「なぜ怖いのかわからないけれど、行こうとすると体が動かない」と感じることもあります。「学校が怖い」理由は一つではなく、複数の要因が重なり合っていることが多いのです。「怖い」という気持ちは、単なるわがままや怠けではなく、お子さんにとって切実な心のサインであると理解していただけたらと思います。
「学校が怖い」理由がよくわからないときの対応

「理由はわからないけれど、怖い…」とお子さんに言われると、親としてはどうしてあげたら良いものか、頭を悩ませてしまいますよね。お子さんを楽にしてあげたいからこそ、理由を知りたい気持ちが強くなられるかもしれません。しかし、理由を問い詰めることはお子さんを追い詰めることになりかねません。理由がわからないときの対応のポイントをご紹介します。
• 無理に原因を聞き出そうとしない
• 「怖いと思っていること自体が大事なサイン」と受け止める
• 理由があってもなくても、学校に行けなくても「あなたは大切な存在」と伝える
• 「学校が怖い」原因にこだわらず、お子さんがご自分の気持ちを言葉化にできるまで待ち、安心できる雰囲気を整える
安心して過ごし、その中で、少しずつ自分の思いを言葉にしていけるようサポートすることが大切です。
• 無理に原因を聞き出そうとしない
• 「怖いと思っていること自体が大事なサイン」と受け止める
• 理由があってもなくても、学校に行けなくても「あなたは大切な存在」と伝える
• 「学校が怖い」原因にこだわらず、お子さんがご自分の気持ちを言葉化にできるまで待ち、安心できる雰囲気を整える
安心して過ごし、その中で、少しずつ自分の思いを言葉にしていけるようサポートすることが大切です。
「学校が怖い」気持ちを和らげる方法
お子さんが「学校が怖い」と感じているとき、まず大切なのは「恐怖心を無理に取り除こうとしない」ことです。取り除こうとすればするほど、「怖い」気持ちを強く意識してしまうことになります。取り除くのではなく、少しずつ安心感を取り戻していく・広げていくことが必要です。具体的な方法をいくつかご紹介します。
怖い気持ちを和らげる方法①安心して気持ちを話せる環境をつくる
「何が怖いの?どうして?」と原因を探ろうとするのではなく、お子さんが話をしてきたときには、「そう感じるんだね、そんなふうに考えていたんだね」とそのままを受け止めてあげましょう。何も話したがらないときは、そばにいてあげるだけで大丈夫です。
怖い気持ちを和らげる方法②安心して過ごせる居場所を整える

安心して過ごせる時間が、心の休養と回復につながります。学校に行けない自分を責めているお子さんが非常に多いです。家でも学校に行けないことを責められてしまうと、さらにお子さんを追い詰めてしまうことになりかねません。まずは、安心して過ごせる居場所を整え、心が充電されてきたら、その範囲を少しずつ広げてみましょう。
怖い気持ちを和らげる方法③小さな成功体験を認める
「今日は笑顔が多いね」「お友達と遊びに出かけられたね」「学校の前まで行けたね」など、お子さんお一人お一人の小さな一歩を発見して、認めることが自信につながります。
怖い気持ちを和らげる方法④外部の力を借りる
親子だけで抱え込まず、スクールカウンセラーや自治体の相談窓口、民間の専門機関等に相談することで、子どもが安心して話すことができ、回復の後押しをしてくれる専門家と繋がれる場合もあります。お子さんが行きたがらない場合は、まずは、親御さんが継続して繋がってみましょう。親御さんの心の安定や変化が、お子さんの力になります。親御さんだけが相談に通うことで、大きく好転したケースも多くあります。
「学校が怖い」お子さんへのNG対応4選

では、親御さんはどのようにお子さんと向き合っていけば良いのでしょうか。まずは、避けていただきたい対応を4つご紹介します。
1. 無理やり登校を迫る
「行きなさい」「休んでばかりでどうするの」と強制すると、恐怖心はさらに強まります。親御さんに対する気遣いや恐怖心から短期的に登校できたとしても、心の負担は軽くならず、再び休んでしまったり、かえって問題が大きくなってしまうこともあります。
2. 「甘えているだけ」と決めつける
甘えていたり、怠惰な様子に見えても、ご本人は苦しんでいて、学校に行けない自分を責めていることが多いです。「甘えているのでは?」「こんなことも耐えられなかったら将来困る」などと責められると、より心に負担がかかり、ふさぎ込んでしまったり、将来に希望が抱けなくなってしまいます。
3. 比較する
きょうだいや友達と比べて「○○ちゃんは行ってるのに」「他の子は頑張ってるのに」と言うことは、お子さんの心をさらに追い詰めることになりかねません。
4. 意思や気持ちを聞かずに解決策を押し付ける
お子さんを心配なあまり、解決策を提示したくなるものです。しかし、「そうできない自分」に苦しんでいたり、お子さんの思いとかけ離れていることも少なくありません。お子さんが自分で答えを見つけられるよう、共感的に話を聞くことが大切です。
「学校が怖い」お子さんへのOK対応6選
つづいて、「学校が怖い」お子さんへの望ましい対応をご紹介します。
1. 共感的に気持ちを受け止める

「怖いんだね」「そんなふうに感じているんだね」と共感的に受け止めることで、お子さんは少しずつ気持ちを言葉にできるようになります。
2. 健康と安心を優先する
登校の有無にこだわるより、まずは家庭で心身を休めることを重視しましょう。不登校に伴って、体調不良を訴えるお子さんも少なくありません。心身ともに安心して休めることが、回復へとつながっていきます。
3. 一緒に小さな目標を立てる
「学校に行く」ことをゴールにせず、「朝ごはんを一緒に食べる」「外に散歩に出る」といった小さな目標から始めるのが効果的です。最初は、登校を見据えた目標ではなく、お子さんの興味や関心に応じて、「やりたい気持ち」や「わくわく感」を引き出すような目標を見つけることをおすすめします。
4. 子どもの興味や得意を伸ばす
絵を描く、音楽を楽しむ、ゲームを通じて友達と交流するなど、好きなことに取り組むことで、自信を取り戻すお子さんも多いです。「学校に行けない自分」ではなく「好きなことができる自分」として生き生きとした自分を発見し、自己肯定感を見出していくことができるのです。
5. 第三者のサポートを利用する

スクールカウンセラー、地域の教育センター、フリースクール、民間の相談機関などを利用することで、親子だけでは見えなかった選択肢が広がります。お子さんの不登校によって、親御さん自身も辛く苦しい思いを抱えていることも多いです。信頼できる専門家と繋がることが、親御さんの支えになり、結果的にお子さんの力になります。
6. 「学校以外の道もある」と伝える
適応指導教室やフリースクール、オルタナティブスクールなどもあります。高校生以上であれば、通信制高校やサポート校などの選択肢もあるでしょう。学校以外にも居場所や学べる場はたくさんあります。「今いる学校が人生のすべてではない」と知ることが、お子さんに安心感を与えます。
「学校が怖い」と感じるお子さんの学校以外の選択肢
「学校に行けないと将来はどうなるのだろう」と不安に思う親御さんは多いでしょう。しかし、地域差はあるものの、多様な学びの場や制度が整ってきており、「学校に行けない=学びが止まる」わけではありません。ここでは、一例ではありますが、学校以外の選択肢をご紹介します。
フリースクール
少人数制で子どものペースに合わせて学べる場所です。授業だけでなく居場所としての機能もあり、同じような悩みを持つ仲間と出会えることが大きな支えになります。
通信制高校
登校日数や学習方法を柔軟に選べるのが通信制高校です。中学生以上の方にとっては、選択肢の一つになるでしょう。自宅学習を中心に進められる学校も多いので、体調や気持ちに合わせて学びを続けられます。多様な背景をもった生徒も多く、「一人じゃないんだ」と、通信制高校で友人や居場所を得られるお子さんもいます。
オンライン学習・家庭学習
最近ではオンライン教材や映像授業も充実しており、自宅にいながら自分のペースで勉強を進めることが可能です。オンライン授業に参加することで、出席日数にカウントするという自治体もあります。「勉強は続けたいけれど学校は怖い」というお子さんにも合いやすい方法です。
地域の居場所や活動

子ども食堂、地域の学習会、ボランティア活動など、学校以外で人と関わる機会も大切です。多様な人に出会い、社会とのつながりを感じることで、孤立感が和らぎます。
大切なのは、「学校に行けない=人生の行き止まりではない」ということです。子どもに合った学びや成長の場は必ずあります。親御さんが選択肢を知り、お子さんと一緒に考えていくことで、未来への希望が広がっていきます。
大切なのは、「学校に行けない=人生の行き止まりではない」ということです。子どもに合った学びや成長の場は必ずあります。親御さんが選択肢を知り、お子さんと一緒に考えていくことで、未来への希望が広がっていきます。
不登校の背景にある「学校が怖い」気持ちとは?―親御さんができるサポートとNG対応 ーまとめー
「学校が怖い」という気持ちを伴う不登校は、お子さんとっても親御さんにとっても大きな試練と感じているかもしれません。不登校の最中は、苦しさや不安がつきまとうものですが、不登校は決して後ろ向きな出来事、人生の汚点ではありません。お子さんが自分の気持ちに気づき、自分の人生の新しい道を模索する大切なターニングポイントにもなるのです。不登校の時間は、決して無駄ではなく、子どもの未来へつながる大切なプロセスです。未来へつながる道を歩んでいく第一歩として、親子だけで抱え込まず、信頼できる伴走者(学校の先生、専門機関、同じ経験を持つ仲間など)を見つけていただけたらと思います。
YSカウンセリングセンターでは
「子どもが不登校でこの先が不安…」
「このままひきこもりになってしまうのでは…」
「不登校の子どもにどうやって接したらいいの」
という親御さんの無料相談を受け付けています。
子どもをよみがえらせるのは、医者でも、薬でも、相談員でもありません。お子さんの回復のカギは、親御さんの「接し方」にあります。ご家庭でのお子さんの様子や親御さんのお悩みなど、じっくりマンツーマンでヒアリングを行い、解決までの道すじを、具体的にご相談いただけます。
経験豊富なカウンセラーが対応いたしますので、少しでも気になる方はお気軽にご連絡ください。
↓ ↓ ↓
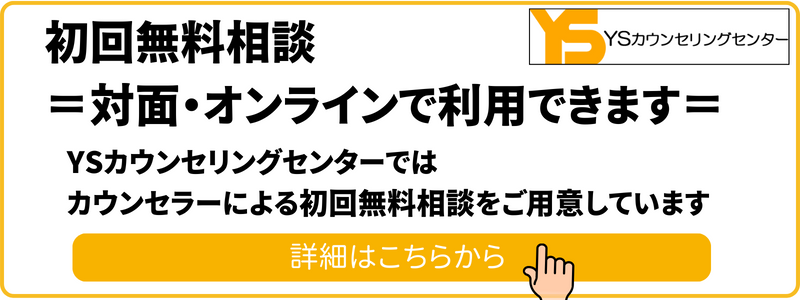
当センターでは、親御さん・ご家族の無料相談を受け付けています
また、「心病むお子さんを救う接し方講座」(無料)も月に1度開催しています。
ぜひお気軽にご参加ください。
「このままひきこもりになってしまうのでは…」
「不登校の子どもにどうやって接したらいいの」
という親御さんの無料相談を受け付けています。
子どもをよみがえらせるのは、医者でも、薬でも、相談員でもありません。お子さんの回復のカギは、親御さんの「接し方」にあります。ご家庭でのお子さんの様子や親御さんのお悩みなど、じっくりマンツーマンでヒアリングを行い、解決までの道すじを、具体的にご相談いただけます。
経験豊富なカウンセラーが対応いたしますので、少しでも気になる方はお気軽にご連絡ください。
↓ ↓ ↓
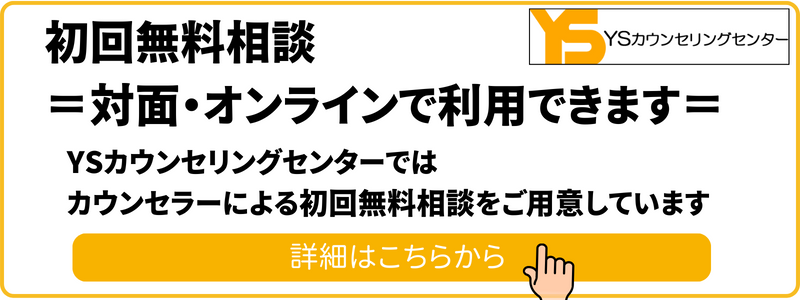
当センターでは、親御さん・ご家族の無料相談を受け付けています
また、「心病むお子さんを救う接し方講座」(無料)も月に1度開催しています。
ぜひお気軽にご参加ください。