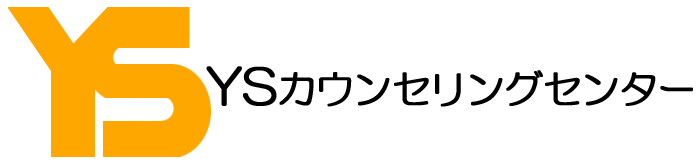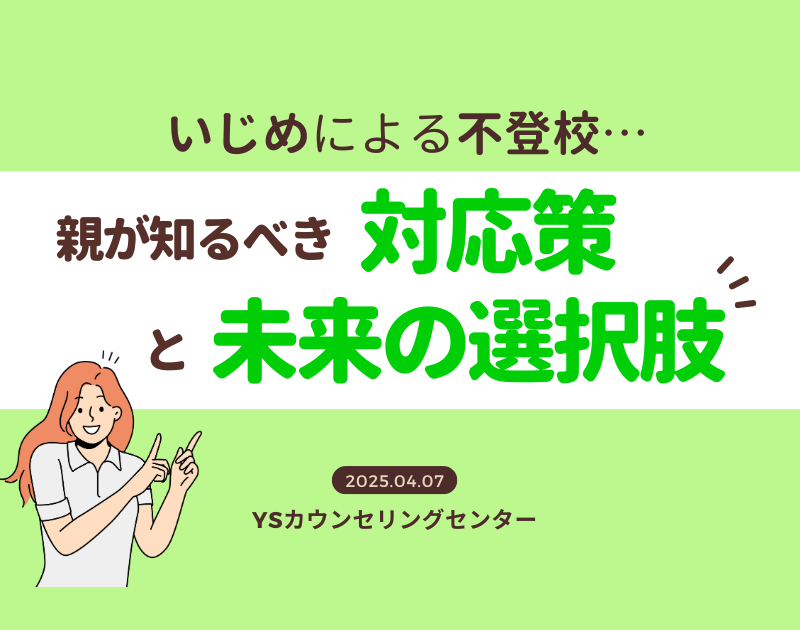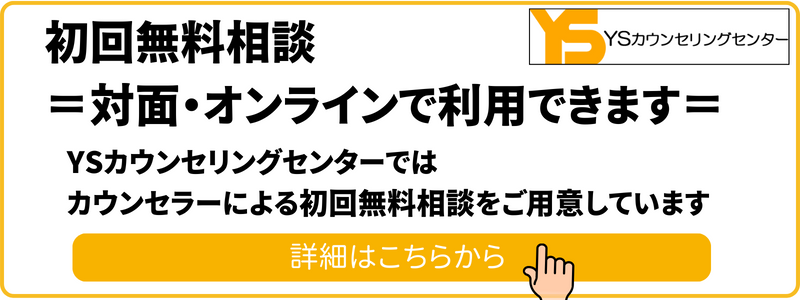この記事を書いた人:武山 円
YSカウンセリングセンターカウンセラー
スクールカウンセラー 公認心理師
いじめによる不登校…親が知るべき対応策と未来の選択肢
「お子さんがいじめを受け、不登校になってしまった——。
親として、胸が張り裂けるほどの思いを抱えていらっしゃるのではないでしょうか。
「学校に行かせてあげたいけれど、無理をさせるわけにもいかない。」
「今の状況がいつまで続くの?将来はどうなるの?」
不安ばかりが募ってしまうことと思います。
「このままで大丈夫なの?」
「どうすれば子どもが前向きになれるの?」
「学校以外に選択肢はあるの?」
そんな疑問や不安を抱えている親御さんに向けて、本記事では、いじめが原因で不登校になったお子さんのために親御さんができること、そして今後の選択肢について詳しくご紹介します。お子さんの未来を明るく照らすために、お役に立てましたら幸いです。

この記事を読んでわかること
いじめによる不登校の実態~文部科学省のデータから見る現状~
文部科学省の調査結果では、「いじめを主たる要因とする不登校」は比較的少ないと報告されています。しかし、実際にそうなのでしょうか。疑問を抱く方も多いのではないかと思います。文部科学省のデータをもとに、いじめによる不登校の実態を整理し、データに反映されにくい「隠れたいじめ不登校」についても考えていきます。
① いじめの認知件数の推移
文部科学省の「令和4年度 児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査」によると、2022年度に全国の小学校、中学校、高等学校、および特別支援学校で把握されたいじめの認知件数は68万1,948件でした。前年度(61万5,351件)と比べて約10.8%増加しており、いじめの件数は年々増加傾向にあることがわかります。
特に小学生のいじめが大きく増えており、2022年度の認知件数は約50万件と、全体の約73%を占めています。
| 年度 | 小学生 | 中学生 | 高校生 |
| 2017年 | 317,121件 | 80,424件 | 14,789件 |
| 2018年 | 425,844件 | 97,704件 | 17,709件 |
| 2019年 | 484,545件 | 106,524件 | 18,352件 |
| 2020年 | 420,897件 | 80,877件 | 13,126件 |
| 2021年 | 500,562件 | 97,937件 | 14,157件 |
| 2022年 | 681,948件 | 122,529件 | 18,462件 |
特に小学生のいじめが大きく増えており、2022年度の認知件数は約50万件と、全体の約73%を占めています。
② 不登校児童生徒数の推移
いじめの認知件数が増加するのと同時に、不登校の児童生徒数も増え続けています。文部科学省の調査結果によると、2022年度の不登校児童生徒数は以下の通りです。
不登校の子どもの数は過去最多を更新し続けており、特に中学生の不登校が約20万人に達している点が特徴的です。
| 年度 | 小学生の不登校 | 中学生の不登校 | 高校生の不登校 |
| 2017年 | 35,032人 | 108,999人 | 49,642人 |
| 2018年 | 44,841人 | 119,687人 | 52,723人 |
| 2019年 | 53,350人 | 127,922人 | 50,100人 |
| 2020年 | 63,350人 | 132,777人 | 43,051人 |
| 2021年 | 81,498人 | 163,442人 | 50,985人 |
| 2022年 | 103,049人 | 195,304人 | 60,575人 |
不登校の子どもの数は過去最多を更新し続けており、特に中学生の不登校が約20万人に達している点が特徴的です。
③ いじめが原因で不登校になった児童生徒の数
文部科学省の調査では、不登校の要因の一つとして「いじめ」が挙げられています。しかし、その割合は比較的低いとされています。2021年度のデータでは、不登校になった子どものうち、いじめが主な原因とされた人数は以下の通りです。
• 小学生:81,498人のうち245人(約0.3%)
• 中学生:163,442人のうち271人(約0.2%)
• 高校生:50,985人のうち104人(約0.2%)
この数値だけを見ると、「いじめが原因で不登校になる子どもは少ない」と思われるかもしれません。しかし、これはあくまで学校の報告に基づくデータであり、実際の数値とは大きく異なる可能性があります。
• 小学生:81,498人のうち245人(約0.3%)
• 中学生:163,442人のうち271人(約0.2%)
• 高校生:50,985人のうち104人(約0.2%)
この数値だけを見ると、「いじめが原因で不登校になる子どもは少ない」と思われるかもしれません。しかし、これはあくまで学校の報告に基づくデータであり、実際の数値とは大きく異なる可能性があります。
④ いじめが原因で不登校になる児童生徒は本当に少ないの?

では実際の数値とは異なる可能性があるとはどういうことか、考えていきたいと思います。
まず、学校がいじめを認識していないケースです。いじめを受けた子どもが先生や親に相談せず、一人で抱え込んでいる状態など、人数には含まれません。また、いじめが原因で「無気力・不安」になり、最終的に不登校に至るケースの場合、文部科学省の調査では「無気力・不安」に分類されるため、「いじめが原因で不登校になった児童生徒」として計上されていないケースがあります。さらに、SNS上でのいじめのなど、従来のいじめの形とは異なる手法が増え、発覚しにくくなっている現状もあります。
これらの要因を考慮すると、いじめによる不登校の実態は、文部科学省のデータ以上に深刻である可能性が高いと言えるのではないでしょうか。
まず、学校がいじめを認識していないケースです。いじめを受けた子どもが先生や親に相談せず、一人で抱え込んでいる状態など、人数には含まれません。また、いじめが原因で「無気力・不安」になり、最終的に不登校に至るケースの場合、文部科学省の調査では「無気力・不安」に分類されるため、「いじめが原因で不登校になった児童生徒」として計上されていないケースがあります。さらに、SNS上でのいじめのなど、従来のいじめの形とは異なる手法が増え、発覚しにくくなっている現状もあります。
これらの要因を考慮すると、いじめによる不登校の実態は、文部科学省のデータ以上に深刻である可能性が高いと言えるのではないでしょうか。
いじめの認知件数が増えた理由
いじめの認知件数が増加した背景について解説します。不登校やいじめは、様々な要因が複雑に絡み合っていることも多く、ここで紹介するものはあくまで一例です。また、これから記す内容があったとしても、必ずいじめが起きるというわけではありません。
いじめによる不登校で悩むお子さんを理解するうえでの一つの背景として、参考にしていただければと思います。
いじめによる不登校で悩むお子さんを理解するうえでの一つの背景として、参考にしていただければと思います。
いじめ増加の背景①スマートフォン・SNSの普及による影響

スマートフォンやSNSの普及により、いじめの形態が大きく変化しました。従来の学校内での身体的・言葉によるいじめに加え、LINEやX(旧Twitter)、Instagram、TikTokなどを利用したネットいじめが増えています。具体的には、SNS上での悪口や誹謗中傷、グループチャットでの悪口、デマの拡散、無視や排除といった行為が増加。SNSの特徴を利用し、匿名のアカウントで誹謗中傷を行うケースもあります。SNSによるいじめの特徴として、学校の外でもいじめが継続し、逃げ場がない状況に陥ることもあげられます。
これらの影響により、学校内だけでなく、24時間365日、家庭に帰ってからもいじめが続くこと、またそのことが表面化しづらいことで、子どもたちの精神的な負担から不登校につながるケースも見られます。
これらの影響により、学校内だけでなく、24時間365日、家庭に帰ってからもいじめが続くこと、またそのことが表面化しづらいことで、子どもたちの精神的な負担から不登校につながるケースも見られます。
いじめ増加の背景②ライフスタイルの変化
ライフスタイルの変化に伴い、核家族や共働きが増加・デジタル機器の普及により、親子間のコミュニケーションが減少していると言われています。そしてそれがいじめが増加している一つの要因だと言われています。
また、インターネットやゲームなどに触れる機会が増えたことも影響を与えています。インターネットやゲーム上での暴力的表現は、子どもたちの人格形成、社会性の成長にマイナスの効果を与える可能性があると言われています。(参考:文部科学省委託調査「青少年を取り巻くメディアと意識・行動に関する調査研究―メディアによって表現された暴力的有害情報が青少年に与える影響に関する文献調査―」)
ここで注意していただきたいのは、「忙しい家庭の子どもがいじめっこになる」「ゲームをしていることがいじめにつながる」という問題ではないということです。一つの時代的背景として、とらえてください。
また、インターネットやゲームなどに触れる機会が増えたことも影響を与えています。インターネットやゲーム上での暴力的表現は、子どもたちの人格形成、社会性の成長にマイナスの効果を与える可能性があると言われています。(参考:文部科学省委託調査「青少年を取り巻くメディアと意識・行動に関する調査研究―メディアによって表現された暴力的有害情報が青少年に与える影響に関する文献調査―」)
ここで注意していただきたいのは、「忙しい家庭の子どもがいじめっこになる」「ゲームをしていることがいじめにつながる」という問題ではないということです。一つの時代的背景として、とらえてください。
いじめ増加の背景③いじめに対する社会的意識の変化
過去に比べ、「いじめはいけないこと」という認識が社会全体で強まってきています。また、芸能人や著名人がメディアでいじめ体験を語ることも増えました。この変化により、いじめを受けた子どもが「いじめを受けることが恥ずかしい」と考えず、相談しやすくなったことも要因の一つです。
また、いじめ防止対策の強化により、学校側が認知するいじめの件数が増え、学校からの報告も増えています。
いじめの認知件数が増えているのは、いじめ自体が増えているという見方だけでなく、社会全体で問題視される傾向が強まり、可視化されるようになったことも一因となっています。
また、いじめ防止対策の強化により、学校側が認知するいじめの件数が増え、学校からの報告も増えています。
いじめの認知件数が増えているのは、いじめ自体が増えているという見方だけでなく、社会全体で問題視される傾向が強まり、可視化されるようになったことも一因となっています。
いじめが原因の不登校に親はどう対応したら良いか

いじめが原因でお子さんが不登校になった場合、親としてどのように対応すればよいのでしょうか。具体的な対応策を詳しくご紹介します。
親の対応①お子さんの気持ちを受け止める
まず、お子さんが直面している状況や感じていることをしっかりと受け止めることが重要です。お子さんが安心して気持ちを話せるよう、以下のポイントを心がけましょう。
・傾聴する姿勢を持つ: お子さんの話を遮らず、最後までしっかりと聞くことで、信頼関係を築きます。
・否定や批判を避ける: お子さんの感じていることを否定せず、共感を示すことで、心の負担を軽減します。
・焦らず待つ: お子さんがいじめられていると知ったとき、心配のあまり、原因を聞きたくなるのは自然なことです。しかし、お子さんが話す準備ができるまで無理に問い詰めないことも大切です。話しても話さなくても「ここに存在して良い」という、安心できる環境を整えましょう。
お子さんが自分の気持ちを理解してもらえると感じることで、心の安定につながります。
・傾聴する姿勢を持つ: お子さんの話を遮らず、最後までしっかりと聞くことで、信頼関係を築きます。
・否定や批判を避ける: お子さんの感じていることを否定せず、共感を示すことで、心の負担を軽減します。
・焦らず待つ: お子さんがいじめられていると知ったとき、心配のあまり、原因を聞きたくなるのは自然なことです。しかし、お子さんが話す準備ができるまで無理に問い詰めないことも大切です。話しても話さなくても「ここに存在して良い」という、安心できる環境を整えましょう。
お子さんが自分の気持ちを理解してもらえると感じることで、心の安定につながります。
親の対応②学校との連携を図る
いじめの問題を解決するためには、学校との連携が不可欠です。学校と協力関係を築いていけると良いでしょう。まずは、担任の先生や養護教諭・スクールカウンセラーなどへ相談してみましょう。お子さんの状況を詳しく伝え、学校の把握している情報やその対応について共通理解を図ります。その際に、具体的な事実の共有をしましょう。いじめの内容や頻度、加害者の情報など、具体的な事実を整理して伝えることで、学校側も適切な対応が取りやすくなります。その後も、学校との連絡を密にし、お子さんの状況や学校側の対応策を共有しましょう。
親の対応③専門機関や第三者への相談
いじめの問題は複雑で、学校とのやりとりだけでは行き詰ってしまうこともあります。その際は、専門機関や第三者のサポートを求めることが有効です。
自治体の教育相談センターでは、いじめや不登校に関する専門的なアドバイスや支援を提供していることも多いです。また、いじめ被害者や不登校の子どもたちを支援するNPO法人や支援団体が各地に存在し、情報提供やカウンセリングを行っています。お子さんの心身の健康状態に不安がある場合、心療内科や精神科の受診を検討することも大切です。
自治体の教育相談センターでは、いじめや不登校に関する専門的なアドバイスや支援を提供していることも多いです。また、いじめ被害者や不登校の子どもたちを支援するNPO法人や支援団体が各地に存在し、情報提供やカウンセリングを行っています。お子さんの心身の健康状態に不安がある場合、心療内科や精神科の受診を検討することも大切です。
親の対応④家庭内で安心して過ごせる環境を整える
家庭がお子さんにとって安心できる場所であるよう、以下の点に注意して、家庭内でサポートしていきましょう。
・日常生活のリズムを整える: できる範囲で規則正しい生活習慣を送ることで心身の健康の回復の助けになります。
・リラックスできる環境の提供: お子さんが趣味や好きなことに集中できる時間や空間を作ることも、心身の回復に役立ちます。
・ご家族の理解と協力: お母さまだけが抱え込んで悩んでいるというケースも多いです。ご本人と相談しながら、ご家族で情報を共有し、協力関係を築けると良いでしょう。
・日常生活のリズムを整える: できる範囲で規則正しい生活習慣を送ることで心身の健康の回復の助けになります。
・リラックスできる環境の提供: お子さんが趣味や好きなことに集中できる時間や空間を作ることも、心身の回復に役立ちます。
・ご家族の理解と協力: お母さまだけが抱え込んで悩んでいるというケースも多いです。ご本人と相談しながら、ご家族で情報を共有し、協力関係を築けると良いでしょう。
親の対応⑤お子さんの自己肯定感を高める

いじめを経験したお子さんは、自信を失っていることが多いです。自己肯定感を取り戻すために、以下のことを実践されてみてください。
・小さな成功体験を積み重ねる: 家事の手伝いや好きなこと、趣味の中でもかまいません。小さな変化を大きく認め、積み重ねていくことが大切です。
・お子さんの良いところを書き出す: 「優しい」「頑張りやさん」「ゲームが得意」など、お子さんの良いところ、素敵なところ、成長したところをたくさん書き出してみましょう。お子さんと会話ができるようでしたら、ぜひ、お子さんに言葉にして伝えてください。
・お子さんが好きなこと、やってみたいこと、ワクワクすることに取り組むことをサポートする: 習い事やボランティア活動などももちろん素敵なことですが、家でできる小さなことからでかまいません。小さな楽しい経験、ワクワクする経験、新しい経験を大切にされてみてください。
自己肯定感の向上は、お子さんの心の回復と将来への希望につながっていきます。
・小さな成功体験を積み重ねる: 家事の手伝いや好きなこと、趣味の中でもかまいません。小さな変化を大きく認め、積み重ねていくことが大切です。
・お子さんの良いところを書き出す: 「優しい」「頑張りやさん」「ゲームが得意」など、お子さんの良いところ、素敵なところ、成長したところをたくさん書き出してみましょう。お子さんと会話ができるようでしたら、ぜひ、お子さんに言葉にして伝えてください。
・お子さんが好きなこと、やってみたいこと、ワクワクすることに取り組むことをサポートする: 習い事やボランティア活動などももちろん素敵なことですが、家でできる小さなことからでかまいません。小さな楽しい経験、ワクワクする経験、新しい経験を大切にされてみてください。
自己肯定感の向上は、お子さんの心の回復と将来への希望につながっていきます。
親の対応⑥無理に登校を促さない
親御さんとしては「学校に行っていない」という事実はご不安になるかと思います。しかし、お子さんの「学校に行きたくない」という気持ちの根底にある不安や恐怖を理解し、無理に登校を強要しないことが大切です。お子さんが人との関わりや学習に前向きな気持ちが出てきている場合は、フリースクールやオンライン学習など、学校以外の学びの場を検討することで、お子さんにとって負担の少ない方法を選ぶこともできます。
また、お子さんの状況が落ち着き、学校復帰に向けて動き出す場合にも、まずは学校の前を一緒に通る、先生と話す機会を作るなど、少しずつ学校とのつながりを取り戻す方法を探し、スモールステップで進んでいくことが大切です。お子さんが安心して前に進めるよう、焦らず寄り添いながらサポートしましょう。
また、お子さんの状況が落ち着き、学校復帰に向けて動き出す場合にも、まずは学校の前を一緒に通る、先生と話す機会を作るなど、少しずつ学校とのつながりを取り戻す方法を探し、スモールステップで進んでいくことが大切です。お子さんが安心して前に進めるよう、焦らず寄り添いながらサポートしましょう。
親の対応⑦親御さん自身の心身のケア
いじめによる不登校は、親にとっても大きなストレスとなる問題です。お子さんの心身の回復・成長には、親御さん自身の心の健康も非常に重要です。そのために、スクールカウンセラー、専門機関、カウンセリングを活用するなどして、相談できる相手を見つけましょう。また、親御さん自身が、好きなことややりたいことをする時間、リラックスできる時間を意識的にとるようにしましょう。
こちらの記事も参考になさってください。
不登校が続いて疲れたあなたへ~お子さんの不登校に疲れた心が楽になる話~
こちらの記事も参考になさってください。
不登校が続いて疲れたあなたへ~お子さんの不登校に疲れた心が楽になる話~
親の対応⑧いじめを乗り越えた先の未来を考える
いじめによる不登校は大きな試練ですが、必ずしも悪いことばかりではありません。この経験を通じて、お子さんが自分に合った生き方や学びの場を見つける機会にもなり得ます。具体的には、
・新しい環境を検討する: 転校やフリースクール、通信制高校など、新しい環境でお子さんが安心して学べる選択肢を検討することも一つの方法です。
・将来の可能性を広げる: 同じ学校に戻ることだけが正解ではありません。お子さんの興味や強みを生かせる分野を一緒に探し、自己理解や自己成長につなげることもできます。
・この経験を通して得た気づきや成長を発見する: まずはいじめの経験の辛さや苦しさを吐き出せることが大切ですが、その先にいじめの経験を通して得られた気づきや成長を振り返り、書き出してみると、大きな一歩につながります。
お子さんの未来にはさまざまな可能性があります。お子さんがご自分の未来に希望を見出せるような関わりをもつことが大切です。
・新しい環境を検討する: 転校やフリースクール、通信制高校など、新しい環境でお子さんが安心して学べる選択肢を検討することも一つの方法です。
・将来の可能性を広げる: 同じ学校に戻ることだけが正解ではありません。お子さんの興味や強みを生かせる分野を一緒に探し、自己理解や自己成長につなげることもできます。
・この経験を通して得た気づきや成長を発見する: まずはいじめの経験の辛さや苦しさを吐き出せることが大切ですが、その先にいじめの経験を通して得られた気づきや成長を振り返り、書き出してみると、大きな一歩につながります。
お子さんの未来にはさまざまな可能性があります。お子さんがご自分の未来に希望を見出せるような関わりをもつことが大切です。
いじめによる不登校からの未来の選択肢
いじめが原因で不登校になったとしても、お子さんには未来の選択肢がたくさんあります。現在の学校に戻る方法を模索するのもひとつの道ですし、別の環境を選ぶことも可能です。お子さんが安心して学び、成長できる場を見つけるために、いくつかの選択肢をご紹介します。
不登校からの選択肢①いじめによる心の問題を根本解決をして再登校する

いじめによる不登校になったとき「いじめがなくなったら登校できるのでは」「加害者が謝罪してくれれば」と、いじめの問題そのものへの対処に力が注がれることが多いです。しかし、実際には不安や恐怖、自信の喪失、自己肯定感の低さなど、お子さんの不登校の背景には、心に抱える課題があります。この課題を解消し、自己肯定感が高まると、いじめに対する捉え方や学校に対する思いが変わってくることも多いです。いじめ問題そのものに対応するだけでなく、お子さんの自己肯定感を高めるような関わりを重ねていくことが大切です。当センターでは、親御さん向けの「心を病むお子さんを救う接し方講座」(無料)も開催しております。ぜひご活用ください。
不登校からの選択肢②転校して新たな環境で学ぶ
現在の学校での再登校が難しい場合は、転校を考えるのも一つの方法です。転校先としては、以下のような選択肢があります。
・別の公立・私立学校
・通信制・定時制高校(高校生)
・フリースクール
転校を検討する際には、お子さんの気持ちを尊重することが大切です。まずは資料請求してみたり、見学してみたりするのも良いでしょう。また、前項で述べた通り、転校し、環境を変えただけで、お子さんが心に抱える問題が解決するわけではありません。新しい環境を検討すると同時に、心の回復もサポートしていきましょう。
・別の公立・私立学校
・通信制・定時制高校(高校生)
・フリースクール
転校を検討する際には、お子さんの気持ちを尊重することが大切です。まずは資料請求してみたり、見学してみたりするのも良いでしょう。また、前項で述べた通り、転校し、環境を変えただけで、お子さんが心に抱える問題が解決するわけではありません。新しい環境を検討すると同時に、心の回復もサポートしていきましょう。
不登校からの選択肢③適応指導教室(教育支援センター)を利用する
適応指導教室(教育支援センター)は、不登校の子どもが少しずつ学校復帰を目指せる施設です。教育委員会が運営しており、学習支援、心理的支援、社会性を育む活動などが行われています。自治体によって異なりますが、個別の学習支援を受けられる、同じ境遇の子どもと交流ができる、出席扱いになる場合があるなどのメリットがあります。適応指導教室は、学校復帰を目指したいけれど、いきなり元のクラスには戻れないというお子さんにとって有効な選択肢です。
不登校からの選択肢④フリースクールに通う
フリースクールは、学校とは異なる自由度の高い学びの場です。学校に行かなくても学習が続けられたり、興味のある分野に集中できたり、個別学習ができたりなどのメリットがあります。フリースクールのカリキュラムや指導方針は多様なので、お子さんに合った場所を探すことが大切です。
不登校からの選択肢⑤通信制高校や定時制高校への進学(中学生以上)
中学生以上のお子さんの場合は、通信制高校や定時制高校を選ぶという選択肢もあります。
通信制高校: 自宅学習が中心で、スクーリング(登校日)が少ない
定時制高校: 昼間または夜間の決まった時間に通う
どちらも多様な背景をもったお子さんが在籍しており、自分の生活スタイルに合わせて学ぶことができるため、不登校経験のあるお子さんの進路先として検討される方が多いです。
通信制高校: 自宅学習が中心で、スクーリング(登校日)が少ない
定時制高校: 昼間または夜間の決まった時間に通う
どちらも多様な背景をもったお子さんが在籍しており、自分の生活スタイルに合わせて学ぶことができるため、不登校経験のあるお子さんの進路先として検討される方が多いです。
不登校からの選択肢⑥高卒認定試験を受けて進学する(高校生の場合)
高校に通うのが難しい場合は、高等学校卒業程度認定試験(高卒認定試験)を受けて大学や専門学校への進学を目指す方法もあります。これにより、高校卒業と同等の資格を得ることができ、将来の選択肢が広がります。
不登校からの選択肢⑦習い事やサークル活動を通じて社会とのつながりを持つ

学校という枠組みにこだわらず、習い事やサークル活動を通じて、学びの場や居場所を見つける方法もあります。学校に行くことだけが学びの場ではありません。お子さんの興味や得意なことを伸ばせる環境を探してみるのも一つの方法です。
不登校からの選択肢⑧別室登校や保健室登校、図書室利用について相談する
登校はできるけれど、教室には入れないという場合には、別室登校や保健室登校、図書室を利用することも選択肢としてあげられます。徐々にステップアップして教室に復帰するというお子さんもいます。ただし、学校によって対応は異なるので、お子さん本人の思い、どのような形なら登校できそうか、学校として対応可能かどうか、学校と相談してみましょう。
いじめによる不登校…親が知るべき対応策と未来の選択肢ーまとめー
いじめによる不登校は、お子さんだけでなく親御さんにとってもつらいものです。しかし、解決の道は必ずあります。そして未来の選択肢も一つではありません。お子さんが安心して次の一歩を踏み出せるように、お子さんが未来に希望を抱けるように、周囲の大人がサポートしていくことが大切です。