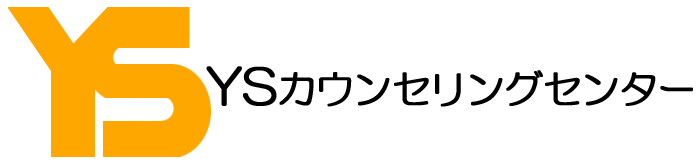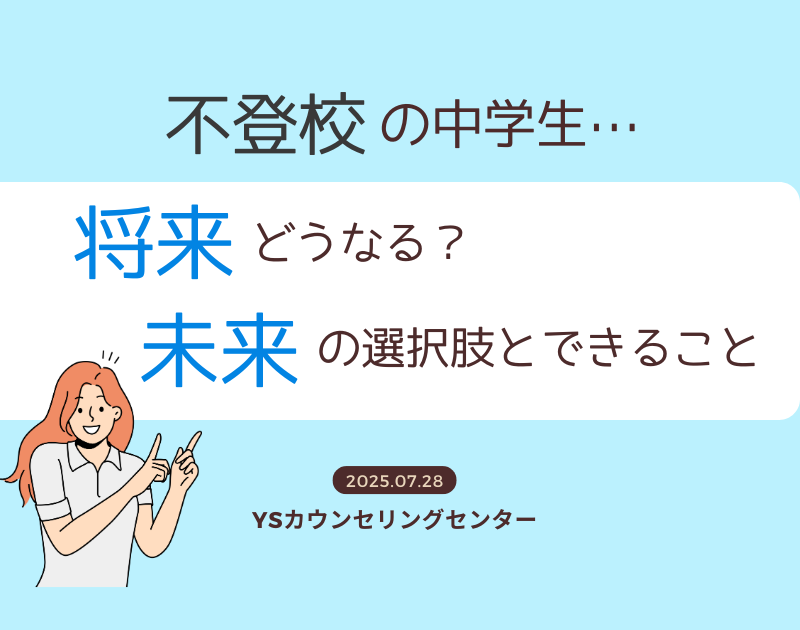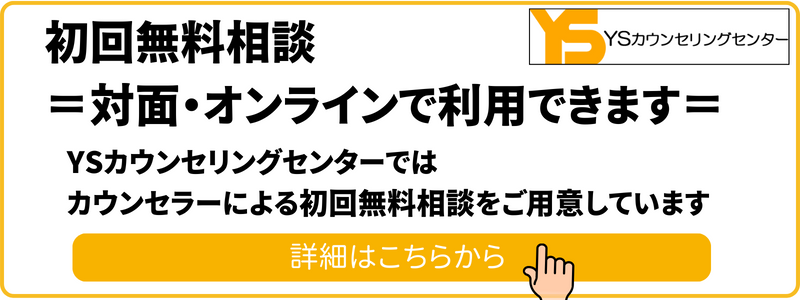この記事を書いた人:武山 円
YSカウンセリングセンターカウンセラー
スクールカウンセラー 公認心理師
不登校の中学生は将来どうなる?未来の選択肢とできること
「このまま学校に行けなかったら、将来どうなってしまうんだろう…」
不登校のお子さんを抱える親御さんの多くが、そんな不安を胸に抱えています。
また、不登校のお子さんご本人も
「社会に出られるのか」
「取り残されるんじゃないか」
と、将来が見えず、強い不安を感じていることが少なくありません。
でも実際には、不登校の経験があっても、自分らしい道を見つけ、
元気に幸せに生きている人たちはたくさんいます。
むしろ、不登校の経験をご自分の財産と感じている方も少なくありません。
この記事では、不登校になった子どもたちの“その後”や選べる進路、そして親としてできる関わり方についてお伝えします。
どうか一人で抱え込まず、「今できること」を一緒に見つけていきましょう。
そして、不登校に悩むすべての方が希望を見出していただけたら幸いです。

この記事を読んでわかること
不登校だった中学生の将来~20歳になったときどうなっているのか~

「このまま学校に行けないまま大人になったら、どうなるのだろう……」
不登校のお子さんを持つ保護者にとって、そんな将来への不安は決して少なくありません。実際に不登校だった中学生はどのような未来をたどっているのでしょうか。
不登校のお子さんを持つ保護者にとって、そんな将来への不安は決して少なくありません。実際に不登校だった中学生はどのような未来をたどっているのでしょうか。
不登校生だった中学生の20歳になった姿とは?
文部科学省が行った追跡調査(平成18年度不登校生徒に関する実態調査報告書)によると、中学3年生のときに不登校だった人のうち、20歳になった時点で「就学・就業している」と回答した人は81.9%にものぼっています。
つまり、約8割の人が高校や大学、専門学校などで学んだり、仕事をして社会と関わっているという結果です。
※出典:文部科学省「不登校に関する実態調査」~平成18年度不登校生徒に関する追跡調査報告書~(平成26年7月9日)
つまり、約8割の人が高校や大学、専門学校などで学んだり、仕事をして社会と関わっているという結果です。
※出典:文部科学省「不登校に関する実態調査」~平成18年度不登校生徒に関する追跡調査報告書~(平成26年7月9日)
8割が就学・就業しているという事実、どうとらえる?
約8割と聞いてほっとする方もいれば、残りの2割は…と不安になる方もいるかもしれません。この調査は、あくまでも20歳の時点での調査で、「浪人していた人」「資格取得の勉強をしていた人」「20歳を過ぎてから進学を目指した人」「20歳を過ぎてから就職活動をして、働き始めた人」なども調査に含まれています。つまり、20歳の時点で所属がない人の中にも、様々な状況が考えられるのです。大切なのは、中学校で不登校を経験していても、将来の道はたくさんあるという事実です。
将来を左右するのは「不登校だったかどうか」ではない

文部科学省の報告書では、不登校だった生徒たちの20歳時点での生活満足度に関する調査も行われています。その中で「現在の生活に満足している」と回答した人の多くは、家族との関係が良好であることや、自分に対する信頼感(自己肯定感)が高いことが共通していると示されています。
つまり、将来を左右するのは「不登校だったかどうか」ではありません。その後、どんな環境でどんな人間関係を築き、どんな心の状態で過ごしてきたかがカギとなるのです。今はまだ動けていない状態でも、「あたたかい人間関係」や「安心できる居場所」、「自己肯定感」を少しずつ取り戻していくことで、未来の選択肢は確実に広がっていきます。人生に“取り返しがつかない時期”などないのです。
つまり、将来を左右するのは「不登校だったかどうか」ではありません。その後、どんな環境でどんな人間関係を築き、どんな心の状態で過ごしてきたかがカギとなるのです。今はまだ動けていない状態でも、「あたたかい人間関係」や「安心できる居場所」、「自己肯定感」を少しずつ取り戻していくことで、未来の選択肢は確実に広がっていきます。人生に“取り返しがつかない時期”などないのです。
不登校でも、将来を怖がらなくて大丈夫
過去に不登校だったお子さんたちの未来の姿についてお伝えしました。とはいえ、見えない未来に恐怖や不安を感じる方も多いのではないでしょうか。そのお気持ちとどのように向き合っていったら良いか、お話したいと思います。
不登校になったとき、将来が不安になるのは自然なこと
不登校になると、「このままで本当に大丈夫なのだろうか」「将来、社会でやっていけるのだろうか」と、多くの方が不安や恐怖を感じます。本人はもちろん、見守る親御さんにとっても、その気持ちは切実です。
学校に通っていないことが、進学や就職、人間関係にどう影響するのか——
不登校に限らず、子どもも大人も、見えない未来への不安は重く感じられるもので、自然な感情です。それだけご自分の人生やお子さんの人生を大切に思っているということです。その恐怖や不安は、決して悪者ではなく、ご自分やお子さんを愛する気持ちの表れなのです。
学校に通っていないことが、進学や就職、人間関係にどう影響するのか——
不登校に限らず、子どもも大人も、見えない未来への不安は重く感じられるもので、自然な感情です。それだけご自分の人生やお子さんの人生を大切に思っているということです。その恐怖や不安は、決して悪者ではなく、ご自分やお子さんを愛する気持ちの表れなのです。
不登校の子どもが将来に不安を抱く理由とは?
「将来が怖い」と感じる理由には、いくつかの背景があります。
• 学校に行けていないことで、自分に対する自信をなくしている
• 同年代の友だちと比べて、取り残されているように感じる
• 「この先もずっと何もできないままかもしれない」という思い込み
• 周囲の期待や“普通であること”へのプレッシャー
これらはすべて、不登校という経験を通して、自分と深く向き合ってきたからこそ生まれる気持ちでもあります。
• 学校に行けていないことで、自分に対する自信をなくしている
• 同年代の友だちと比べて、取り残されているように感じる
• 「この先もずっと何もできないままかもしれない」という思い込み
• 周囲の期待や“普通であること”へのプレッシャー
これらはすべて、不登校という経験を通して、自分と深く向き合ってきたからこそ生まれる気持ちでもあります。
怖さの中から生まれる、新しい力もある

不安や怖さに包まれていると、先のことが何も見えないように感じてしまうものです。けれど、その心があるからこそ生まれるものもあるのです。不登校の経験を通して、ご自分の人生・生き方と真剣に向き合い、見つめ直す機会になったり、家族関係がさらに良くなる機会となったり、人の痛みに深く寄り添えるようになったり、多様な価値観を受け入れる柔軟性を得たりするなど、「不登校になって良かった」と語る方も少なくありません。不登校という経験が、後の人生の財産にもなり得るのです。あなたの道は必ず開けていきます。
不登校でも、選べる進路はたくさんある
「学校に行けていない」ことで、進学や将来の選択肢が狭まってしまうのではと不安に感じる方も多いかもしれません。
しかし実際には、さまざまな進路の選択肢が用意されています。大切なのは、「まわりと同じ道を歩むこと」ではなく、自分に合った道を見つけることです。
ここからは、様々な進路の選択肢をご紹介します。
しかし実際には、さまざまな進路の選択肢が用意されています。大切なのは、「まわりと同じ道を歩むこと」ではなく、自分に合った道を見つけることです。
ここからは、様々な進路の選択肢をご紹介します。
通信制高校:自分のペースで学べるスタイル
通信制高校は、登校日が限られており、自宅中心の学習で卒業を目指せる仕組みです。
自分の体調や気持ちに合わせて、無理のないペースで進められるため、安心して学びを続けやすいというメリットがあります。最近は、進学指導やカウンセリングのサポートが充実している学校も多いです。
自分の体調や気持ちに合わせて、無理のないペースで進められるため、安心して学びを続けやすいというメリットがあります。最近は、進学指導やカウンセリングのサポートが充実している学校も多いです。
定時制高校:少人数で落ち着いた環境
定時制高校は、昼間や夜間など時間帯を選んで通えるスタイルです。一人ひとりの状況に合わせた学び方ができ、人との距離感がちょうどよく感じられるという声もあります。勉強をやり直したい、社会に少しずつなじみたいという人にとって、安心できる選択肢となるかもしれません。
サポート校・フリースクール:心の居場所としての役割
サポート校やフリースクールでは、学びだけでなく心のケアや居場所としての支援も重視されています。「勉強以前に、まず安心できる場所がほしい」「自分らしく過ごせる環境がほしい」といった気持ちに寄り添ってくれるため、少しずつ社会との接点を取り戻すきっかけにもなります。
高卒認定を経て、大学進学へ
高校に行けなかった、卒業できなかったとしても、高卒認定試験(旧大検)を受けることで大学や専門学校の受験資格を得られます。通学ではなく独学や塾、サポート校を利用して学び直すことができるため、「今はまだ高校に通うのは難しい」という人にとっても、希望のある選択肢です。
好きを深める専門学校という道

不登校の経験を通じて、「自分が本当に好きなことに気づけた」という人もいます。
美容・デザイン・調理・介護・ITなど、専門学校は“得意”や“好き”を職業に結びつける場所でもあります。学びながら将来の仕事を具体的に描けるのも魅力です。
美容・デザイン・調理・介護・ITなど、専門学校は“得意”や“好き”を職業に結びつける場所でもあります。学びながら将来の仕事を具体的に描けるのも魅力です。
アルバイトやインターンからの社会経験
学業以外にも、アルバイトやインターンを通じて社会にふれることで、自分のペースで自信を取り戻していく人も多くいます。いきなり正社員を目指すのではなく、「まずは週に数回のバイトから」など、段階的に働く体験を重ねることも立派な進路です。
オンラインや独自のルートで未来を拓く
最近では、留学、オンラインスクールやリモートワーク、副業や個人での起業といった新しい働き方や学び方も広がっています。
「人と同じじゃなくてもいい」「自分らしい道を選びたい」と思える時代だからこそ、進路も柔軟に考えることができます。
「人と同じじゃなくてもいい」「自分らしい道を選びたい」と思える時代だからこそ、進路も柔軟に考えることができます。
不登校経験者が後悔していること「もっと相談していれば」

不登校の子どもたちの中には、大人になってからこう振り返る人もいます。
• 「あのとき、本当は助けを求めたかった」
• 「ひとりで悩みすぎて、時間をムダにしてしまった気がする」
• 「もっと早く誰かに話していれば、何かが変わったかもしれない」
こうした後悔は、当時まわりに頼る方法を知らなかったり、誰かに迷惑をかけることがこわかったり、そんな気持ちが積み重なって生まれるものです。だからこそ、本人が言葉にできなくても、そばにいる大人が手を差し伸べることが何よりの支えになります。
その手は、親だけでなく学校外の大人や第三者でもいいのです。親だからこそ、「心配かけるのではと思うと話しづらい」というお子さんもいます。
信頼できるカウンセラーや支援機関とつながることで、「相談できる人がいる」という安心感を持つことができ、それが新しい一歩の後押しになります。
• 「あのとき、本当は助けを求めたかった」
• 「ひとりで悩みすぎて、時間をムダにしてしまった気がする」
• 「もっと早く誰かに話していれば、何かが変わったかもしれない」
こうした後悔は、当時まわりに頼る方法を知らなかったり、誰かに迷惑をかけることがこわかったり、そんな気持ちが積み重なって生まれるものです。だからこそ、本人が言葉にできなくても、そばにいる大人が手を差し伸べることが何よりの支えになります。
その手は、親だけでなく学校外の大人や第三者でもいいのです。親だからこそ、「心配かけるのではと思うと話しづらい」というお子さんもいます。
信頼できるカウンセラーや支援機関とつながることで、「相談できる人がいる」という安心感を持つことができ、それが新しい一歩の後押しになります。
不登校のお子さんの将来のために親御さんにできる5つの対応
不登校の子どもと向き合うとき、どう接していいか悩む親御さんは多いと思います。
「このままで将来は大丈夫?」「無理にでも学校に行かせたほうがいいの?」――そんな思いを抱えながらも、正解の見えない日々に心が疲れてしまうこともあるでしょう。ですが、お子さんが一番望んでいるのは、「変わらなければ受け入れてもらえない」ことではなく、「そのままの自分で、ここにいていい」という安心感です。
ここでは、不登校の子どもを支えるために親御さんができる5つの対応をご紹介します。
「このままで将来は大丈夫?」「無理にでも学校に行かせたほうがいいの?」――そんな思いを抱えながらも、正解の見えない日々に心が疲れてしまうこともあるでしょう。ですが、お子さんが一番望んでいるのは、「変わらなければ受け入れてもらえない」ことではなく、「そのままの自分で、ここにいていい」という安心感です。
ここでは、不登校の子どもを支えるために親御さんができる5つの対応をご紹介します。
① 「学校に行かなくても、あなたの価値は変わらない」と伝える
学校に行っていないことで、自分の存在を責めている子どもたちは多いです。
だからこそ、まずは、登校の有無に関係なく、「あなたは大切な存在だよ」というメッセージを伝えてあげてください。親御さんから伝えられることで、安心感と自己肯定感につながっていきます。
だからこそ、まずは、登校の有無に関係なく、「あなたは大切な存在だよ」というメッセージを伝えてあげてください。親御さんから伝えられることで、安心感と自己肯定感につながっていきます。
② 話さなくても、そばにいるよという姿勢で
子どもが口を閉ざしているとき、「何を考えているの?」「ちゃんと話して」と問い詰めたくなることもあるかもしれません。特に、不登校の場合、その原因を探りたくなるものです。ですが、お子さん自身が、原因がわからなかったり、言葉にならない思いを抱えていたりします。言葉にならない気持ちを抱えているときほど、そばにいてくれる安心感が心を支えてくれます。無理に聞き出そうせず、お子さんのことをわかってあげたいという気持ちでそばにいることが、心を開く第一歩につながります。
③ 家庭を「安心できる居場所」にする
学校や社会で安心を感じられない今、子どもにとって家庭は「唯一の避難所」になることがあります。だからこそ、家ではプレッシャーをかけずに、リラックスして過ごせる空間づくりを心がけてみてください。心のエネルギーが回復してきて、好きなことができるのも大切なことですが、「何もしなくてもいい時間」も必要なことです。お子さんが“頑張らなくていい自分”を取り戻すことができるようになります。
④ 親御さんご自身が、ひとりで抱え込まない
「親だから、しっかり支えなければ」と思うほど、つらくなってしまうこともあります。でも、親御さんもまた悩み、迷うのが自然なことですし、お子さんを愛すればこその感情です。親御さん自身の生活や心のケアを大切にしてください。親御さんが安心して過ごしていると、お子さんにも自然と安心感が伝わります。
⑤ 専門家の力を借りて、親子で安心できる環境を整える

「どうしていいか分からない」と感じたときは、信頼できる第三者に相談することも大切な選択肢です。学校関係者だけでなく、医療機関、自治体の相談窓口、民間の支援団体など、専門家とつながる手段はいくつもあります。
専門家に話を聞いてもらうことで、
• 子どもの気持ちや状態を客観的に理解できる
• 親としてどう関わればよいかのヒントが得られる
• 親自身のストレスや不安も和らげられる
といったメリットがあります。ときには、親子の間に立ってサポートしてくれる役割を担ってくれることもあります。ひとりで背負わず、専門家と一緒に“伴走”していくという選択が、親子どちらにとっても心強い支えになります。
YSカウンセリングセンターでも、個別相談やお子さんの接し方を学べる講座(無料)を実施しておりますので、ぜひご活用ください。
以上のように、「何か特別なことをしなければ」と気負う必要はありません。
日常のなかで、少しずつ安心を積み重ねていくことが、お子さんにとっての「前に進む力」になります。お子さんの中に、自立する力はあるのです。
専門家に話を聞いてもらうことで、
• 子どもの気持ちや状態を客観的に理解できる
• 親としてどう関わればよいかのヒントが得られる
• 親自身のストレスや不安も和らげられる
といったメリットがあります。ときには、親子の間に立ってサポートしてくれる役割を担ってくれることもあります。ひとりで背負わず、専門家と一緒に“伴走”していくという選択が、親子どちらにとっても心強い支えになります。
YSカウンセリングセンターでも、個別相談やお子さんの接し方を学べる講座(無料)を実施しておりますので、ぜひご活用ください。
以上のように、「何か特別なことをしなければ」と気負う必要はありません。
日常のなかで、少しずつ安心を積み重ねていくことが、お子さんにとっての「前に進む力」になります。お子さんの中に、自立する力はあるのです。
不登校の中学生は将来どうなる?未来の選択肢とできることーまとめー
不登校という経験は、決して「失敗」や「遅れ」ではなく、自分と向き合う大切な時間でもあります。
むしろその時間を経て、自分に合った生き方や、かけがえのない財産を見つけていく人もたくさんいます。
今はまだ将来が見えなくても、「安心できる場所」「味方がいること」「一歩ずつでいい」ということが伝われば、子どもは少しずつ自分の力で進んでいくことができます。
そのために必要なのは、完璧な支援や特別な言葉ではなく、ありのままを受け止めてくれる関係と、必要なときに相談できる支援です。
むしろその時間を経て、自分に合った生き方や、かけがえのない財産を見つけていく人もたくさんいます。
今はまだ将来が見えなくても、「安心できる場所」「味方がいること」「一歩ずつでいい」ということが伝われば、子どもは少しずつ自分の力で進んでいくことができます。
そのために必要なのは、完璧な支援や特別な言葉ではなく、ありのままを受け止めてくれる関係と、必要なときに相談できる支援です。