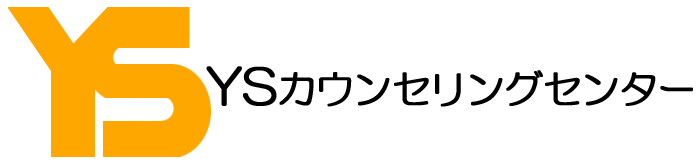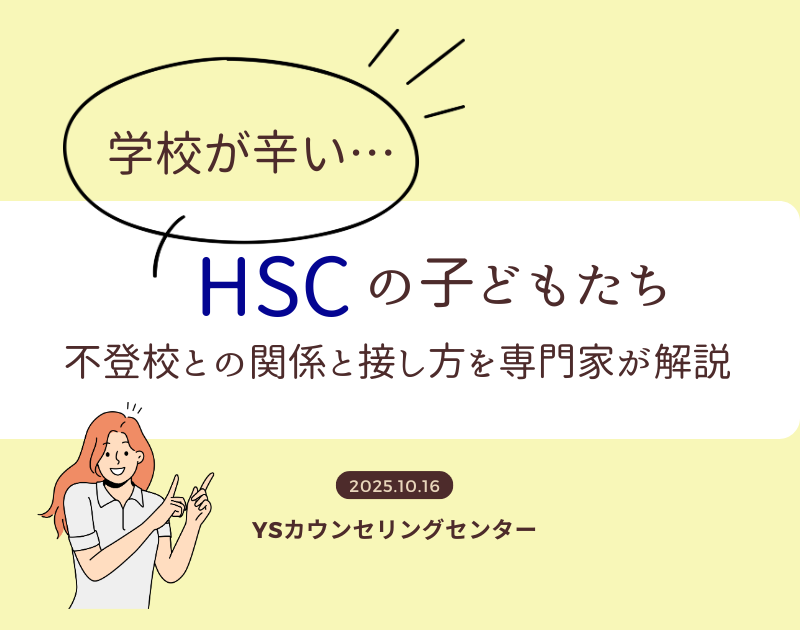この記事を書いた人:武山 円
YSカウンセリングセンターカウンセラー
スクールカウンセラー 公認心理師
学校が辛いHSCの子どもたち――不登校との関係と接し方を専門家が解説
「朝になると泣いてしまう」
「お腹が痛いと言って学校へ行けない」
そんなお子さんの姿を前に、どう声をかけてよいのか分からず悩む親御さんは少なくありません。
特に、HSC(ひといちばい敏感な子)の気質を持つお子さんは、周囲の変化や人の感情に敏感で、学校という集団生活の中で強いストレスを感じやすい傾向があります。HSCの子どもたちは、友達の何気ない一言や先生の表情、小さな失敗を深く受け止めてしまうことがあります。
「ちゃんとしなきゃ」
「怒られたらどうしよう」
と自分を責め続けるうちに、心も体も疲れてしまい、結果として不登校という形で限界を訴えることもあります。
しかし、これは「甘え」や「怠け」ではありません。
HSCの繊細さは、生まれつき持っている大切な個性であり、周囲が理解し、接し方を変えることで、安心して過ごしていけるようになります。
お子さんが学校に行けなくなった背景には、必ずその子なりの理由とサインがあります。
この記事では、「不登校 HSC」 というテーマのもと、HSCの基本的な特徴から、不登校との関係、そしてご家庭での具体的な接し方や支援のポイントまで、わかりやすく解説します。
読み終えるころに、今の不安が少し軽くなり、希望を感じていただけることを願っています。

この記事を読んでわかること
HSCとは?――ひといちばい敏感な子どもの気質について
「HSC」とは Highly Sensitive Child(ハイリー・センシティブ・チャイルド) の略で、日本語では「ひといちばい敏感な子」と訳されます。アメリカの心理学者エレイン・N・アーロン博士によって提唱された概念で、生まれつき感受性が高く、外部からの刺激や周囲の雰囲気を敏感に感じ取りやすい子どもを指します。
HSCの気質を持つお子さんは、人口の約2割程度といわれ、特別に珍しいわけではありません。しかし、その繊細さゆえに学校生活ではストレスを感じやすく、不登校につながるケースも少なくありません。
HSCの気質を持つお子さんは、人口の約2割程度といわれ、特別に珍しいわけではありません。しかし、その繊細さゆえに学校生活ではストレスを感じやすく、不登校につながるケースも少なくありません。
HSCの主な特徴

HSCのお子さんには、次のような特徴がよく見られます。
• 感覚が鋭い:大きな音や強い光、人混みなどに強い疲労や不快感を覚える。
• 感情に敏感:周囲の人の表情や声のトーンにすぐ気づき、相手の気持ちを敏感に察知する。
• 深く考える傾向:物事をじっくり考えすぎて、行動に移すまでに時間がかかることがある。
• 傷つきやすい:失敗や叱責を強く受け止め、長く引きずってしまうことがある。
• 共感力が高い:友達や家族の感情に寄り添いやすく、優しさが際立つ一方で疲れやすい。
これらの特徴は、子どもの性格や環境によって強く表れる場合もあれば、部分的にあてはまる程度のこともあります。大切なのは、「HSCは病気や障害ではなく、生まれ持った気質である」という理解です。
HSCの特徴を知ることで、お子さんが「どうして学校生活で疲れてしまうのか」「なぜ不登校になってしまうのか」を理解する手がかりになります。そして同時に、適切なサポートや環境づくりによって、その敏感さを強みへと活かしていくこともできるのです。
• 感覚が鋭い:大きな音や強い光、人混みなどに強い疲労や不快感を覚える。
• 感情に敏感:周囲の人の表情や声のトーンにすぐ気づき、相手の気持ちを敏感に察知する。
• 深く考える傾向:物事をじっくり考えすぎて、行動に移すまでに時間がかかることがある。
• 傷つきやすい:失敗や叱責を強く受け止め、長く引きずってしまうことがある。
• 共感力が高い:友達や家族の感情に寄り添いやすく、優しさが際立つ一方で疲れやすい。
これらの特徴は、子どもの性格や環境によって強く表れる場合もあれば、部分的にあてはまる程度のこともあります。大切なのは、「HSCは病気や障害ではなく、生まれ持った気質である」という理解です。
HSCの特徴を知ることで、お子さんが「どうして学校生活で疲れてしまうのか」「なぜ不登校になってしまうのか」を理解する手がかりになります。そして同時に、適切なサポートや環境づくりによって、その敏感さを強みへと活かしていくこともできるのです。
不登校とHSCの関係性
HSCのお子さんが必ず不登校になるというわけではありません。しかし、その敏感さゆえに学校生活でさまざまなストレスを抱えやすく、それが不登校につながる大きな要因になることがあります。学校は授業や友人関係、行事など多くの刺激に満ちており、HSCの子どもにとっては一日を過ごすだけで心身ともに大きなエネルギーを消耗します。その結果、次のような状況が起こりやすいのです。
HSCのお子さんが不登校になりやすい背景
•人間関係の摩擦を過度に気にしてしまう
友達の小さな言動や先生の表情の変化を深刻に受け止め、不安や緊張が強くなる。
•学校の集団生活に適応しづらい
騒がしい教室や大人数での行動が苦手で、心身の疲れが蓄積しやすい。
•完璧主義の傾向
小さな失敗や叱責を強く気にしてしまい、自己肯定感が下がる。
•強いストレス反応
朝になると頭痛や腹痛など身体の不調として現れ、登校が難しくなることがある。
友達の小さな言動や先生の表情の変化を深刻に受け止め、不安や緊張が強くなる。
•学校の集団生活に適応しづらい
騒がしい教室や大人数での行動が苦手で、心身の疲れが蓄積しやすい。
•完璧主義の傾向
小さな失敗や叱責を強く気にしてしまい、自己肯定感が下がる。
•強いストレス反応
朝になると頭痛や腹痛など身体の不調として現れ、登校が難しくなることがある。
HSCは「甘え」や「わがまま」ではない

HSCのお子さんの不登校は、決して怠けやわがままから起こるものではありません。人一倍敏感な感覚と気質を持っているからこそ、学校生活の中で強いストレスを感じやすいのです。
そのため、親御さんが「みんなはできているのに…みんな頑張っているのに…」と責めたり、無理に登校させようとしたりすることは、さらに負担を大きくしてしまう可能性があります。
HSCと不登校の関係を正しく理解することが、まずはサポートの第一歩になります。
そのため、親御さんが「みんなはできているのに…みんな頑張っているのに…」と責めたり、無理に登校させようとしたりすることは、さらに負担を大きくしてしまう可能性があります。
HSCと不登校の関係を正しく理解することが、まずはサポートの第一歩になります。
HSCが学校でストレスを感じるとき
HSC(ひといちばい敏感な子)にとって、学校はたくさんの刺激にあふれた場所です。毎日の授業、友達との関わり、先生の指導、そして校内の音や雰囲気――それら一つひとつが、HSCの子どもにとっては強いストレスになることがあります。
1. 集団の中でのプレッシャー
学校では集団行動が求められます。そんな中で、HSCのお子さんは周囲の空気を敏感に感じ取り、「迷惑をかけたくない」「間違えたらどうしよう」と過剰に気をつかってしまうことがあります。これが続くと、教室にいるだけで心が疲れてしまうのです。
2. 先生や友達との関係に敏感
先生のちょっとした言い方や表情、友達の反応などを深読みしてしまい、「嫌われたかもしれない」「怒らせてしまったのでは」と不安に感じやすい傾向があります。こうした不安が積み重なると、学校に行くこと自体が怖くなることもあります。
3. 環境から受ける刺激
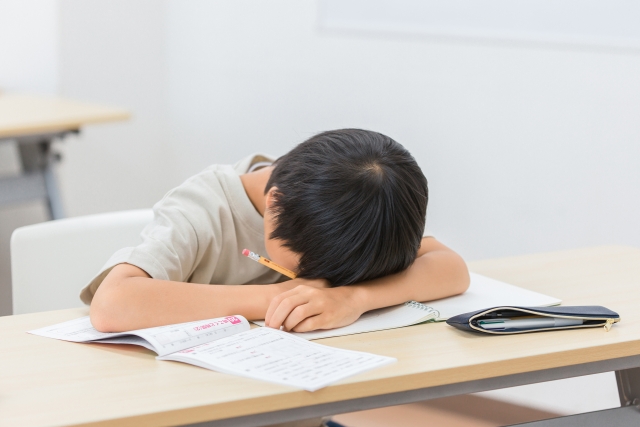
教室のざわめき、チャイムの音、照明の明るさなど、他の子が気にならないような刺激でも、HSCのお子さんには強く感じられることがあります。長時間その環境にいることで、頭痛や吐き気、強い疲労感が出る場合もあります。
4. 完璧主義からくるストレス
「失敗してはいけない」「ちゃんとしなきゃ」という思いが強いHSCの子は、テストや発表、運動会などで自分を過度に追い込みがちです。その結果、緊張や不安で体調を崩し、不登校という形で心と体が「休みたい」というサインを出すこともあります。
HSCのお子さんが学校でストレスを感じているとき、親御さんや先生ができることは「無理に頑張らせること」ではなく、「どうすれば安心して過ごせるか」を一緒に考えることです。
次の章では、HSCで不登校になったお子さんへの対処法と支援の方法について、具体的に見ていきましょう。
HSCのお子さんが学校でストレスを感じているとき、親御さんや先生ができることは「無理に頑張らせること」ではなく、「どうすれば安心して過ごせるか」を一緒に考えることです。
次の章では、HSCで不登校になったお子さんへの対処法と支援の方法について、具体的に見ていきましょう。
HSCで不登校のお子さんへの対処方法・支援方法
HSC(ひといちばい敏感な子)が不登校になる背景には、学校生活でのストレスや人間関係のプレッシャーがあります。親御さんができるサポートの第一歩は、「登校させること」よりも「安心させること」です。
お子さんの心の疲れを癒し、回復へのきっかけを作るために、以下のような支援方法を意識してみましょう。
お子さんの心の疲れを癒し、回復へのきっかけを作るために、以下のような支援方法を意識してみましょう。
1. まずは「安心できる居場所」をつくる
不登校のHSCは、外の世界で消耗した心を守るために「家にいる」ことを選んでいる場合があります。そのため、家を「安心していられる場所」にすることがとても大切です。無理に登校を促したり、説得したりするよりも、
「今はゆっくり休んでいいよ」「よく頑張ったね」
と伝えることで、子どもの心が落ち着いていきます。好きなことばかりしている子どもに苛立ちや腹立たしさを感じるという親御さんも多いですが、充電していると捉え、お子さんが安心して過ごせることを大切にしましょう。
「今はゆっくり休んでいいよ」「よく頑張ったね」
と伝えることで、子どもの心が落ち着いていきます。好きなことばかりしている子どもに苛立ちや腹立たしさを感じるという親御さんも多いですが、充電していると捉え、お子さんが安心して過ごせることを大切にしましょう。
2. 否定せずに聴き、お子さんの良さや頑張りを認める
HSCのお子さんは、人の言葉や態度を深く受け止める傾向があります。「そんなことで休んじゃダメ」と否定するのではなく、
「つらかったね」「そう感じたんだね」
と受け止めることが、再び前を向く力につながります。
また、お子さんが休み始めたとき、心配や不安からお子さんのできていないことや苦手なことばかりに目が向いてしまうことが多いです。お子さんの良さや頑張りを見つけて、大きく認めてあげましょう。
「つらかったね」「そう感じたんだね」
と受け止めることが、再び前を向く力につながります。
また、お子さんが休み始めたとき、心配や不安からお子さんのできていないことや苦手なことばかりに目が向いてしまうことが多いです。お子さんの良さや頑張りを見つけて、大きく認めてあげましょう。
3. 家族全体でサポートする

不登校の問題は、子どもだけではなく、家族全体に影響します。兄弟や夫婦間での理解のズレが、子どもに新たなストレスを与えることも少なくありません。だからこそ、家族全体で「どのように支えていくか」を話し合うことが大切です。
必要に応じて、カウンセリングや家族プログラムを通じて専門家と一緒に取り組むことで、家庭内のサポート体制を整えることができます。
必要に応じて、カウンセリングや家族プログラムを通じて専門家と一緒に取り組むことで、家庭内のサポート体制を整えることができます。
4. 専門家・カウンセラーと連携する
不登校は様々な背景があり、また長期にわたることもあり、家庭だけで抱え込むのは難しいこともあります。専門家と一緒にお子さんの状態・ご家族の状況を整理し、支援方法を検討すると、再び社会とのつながりを回復する道が見えてきます。個別相談を受けた方から、「すっきりしました。『家庭で何をすればよいのか』『どう声をかけたらよいのか』がわかりました」という声もよくお聞きします。
5. 少しずつ「外」とのつながりを取り戻す
十分に休息が取れ、安心感が回復してきたら、フリースクールやオンライン学習、カウンセリング等を通じて少しずつ外との関係を取り戻していきましょう。学校復帰を進める場合にも、できる限りハードルを下げて、小さな小さなステップを設定します。焦らず、「一歩進めたね」と認めてあげることが大切です。
HSCのお子さんの不登校は、「本人の努力不足」ではありません。親が一人で抱え込まず、専門家と一緒に考えることで、確実に解決への道が近づきます。
HSCのお子さんの不登校は、「本人の努力不足」ではありません。親が一人で抱え込まず、専門家と一緒に考えることで、確実に解決への道が近づきます。
HSCのお子さんへの接し方
HSC(ひといちばい敏感な子)のお子さんが不登校になったとき、親御さんがどのように接するかは、回復への大切なカギになります。HSCの子どもは、周囲の感情や言葉を非常に敏感に感じ取るため、親の表情や一言が大きく影響することがあります。ここでは、HSCのお子さんに安心を与え、自信を取り戻すための接し方を紹介します。
1. 「受け止める」姿勢を大切にする

まずは、子どもの気持ちを否定せずに、お子さんを理解したいという気持ちで受け止めることが大切です。「どうして行けないの?」と問い詰めるよりも、「つらかったんだね」「頑張ってきたね」と声をかけることで、子どもの心に「理解してもらえた」という安心感が生まれます。HSCのお子さんは共感力が高いため、親御さんの安心した表情や穏やかな言葉が、そのままお子さんの安心につながります。
2. 「励ます」よりも「寄り添う」
HSCのお子さんにとって、「頑張って」「行けるよ」という励ましの言葉は、時にプレッシャーとして感じられることがあります。代わりに「一緒に考えよう」「あなたのペースで大丈夫」という言葉を選ぶことで、信頼関係が深まります。
3. 安心できる日常リズムを整える
不登校の期間は、生活リズムが乱れやすくなります。それもお子さんが自分を守るために必要な時もありますが、HSCのお子さんは環境の変化に敏感なので、朝起きる時間・食事の時間・就寝時間を一定に保つだけでも、心が落ち着きやすくなります。無理なく続けられるリズムを、家族で一緒に考えていきましょう。
4. 「比較しない」「焦らせない」
「他の子は行けているのに…」という比較は、お子さんの自尊心を傷つけてしまいます。HSCのお子さんは、自分を責める傾向が強いので、「あなたはあなたのままでいい」「学校に行けても行けなくても、大切な存在」と伝えることが大切です。焦らず、安心できる時間の中で、その子のペースで歩んでいけるよう見守っていきましょう。
5. 親もひとりで抱え込まない

HSCのお子さんを支える親御さん自身も、心身の疲れを感じやすいものです。お子さんとずっと一緒に過ごすことで煮詰まることもあるでしょう。ときには「どう接したらいいのか分からない」と迷うこともあるのではないでしょうか。定期的に、カウンセラー等に話すことで、ご自分の気持ちを整理したり、方向性を確認していくことが大切です。家庭だけで抱え込まず、第三者の視点を取り入れることで、より穏やかにお子さんを支えられるようになります。
HSCのお子さんとの関わりで大切なのは、「変えよう」とすることではなく、「理解しよう」とすること、そして「ありのままを認める」ことです。その理解が深まるほど、子どもは安心し、自分らしいペースで歩み始めます。
HSCのお子さんとの関わりで大切なのは、「変えよう」とすることではなく、「理解しよう」とすること、そして「ありのままを認める」ことです。その理解が深まるほど、子どもは安心し、自分らしいペースで歩み始めます。
学校が辛いHSCの子どもたち――不登校との関係と接し方を専門家が解説 ーまとめー
HSC(ひといちばい敏感な子)は、生まれ持った繊細さゆえに、学校生活や人間関係の中で強いストレスを感じやすい気質です。その敏感さが不登校という形で表れることもありますが、それは決して「弱さ」ではなく、「感じ取る力が豊かな証」です。「深い優しさ」や「豊かな感受性」という大きな力です。大切なのは、無理に変えようとすることではなく、「お子さんが安心して過ごせる環境を整えること」。そして、親御さん自身も孤立せず、専門家とつながりながら、少しずつ解決の糸口を見つけていくことです。
YSカウンセリングセンターでは
「子どもが不登校でこの先が不安…」
「このままひきこもりになってしまうのでは…」
「不登校の子どもにどうやって接したらいいの」
という親御さんの無料相談を受け付けています。
子どもをよみがえらせるのは、医者でも、薬でも、相談員でもありません。お子さんの回復のカギは、親御さんの「接し方」にあります。ご家庭でのお子さんの様子や親御さんのお悩みなど、じっくりマンツーマンでヒアリングを行い、解決までの道すじを、具体的にご相談いただけます。
経験豊富なカウンセラーが対応いたしますので、少しでも気になる方はお気軽にご連絡ください。
↓ ↓ ↓
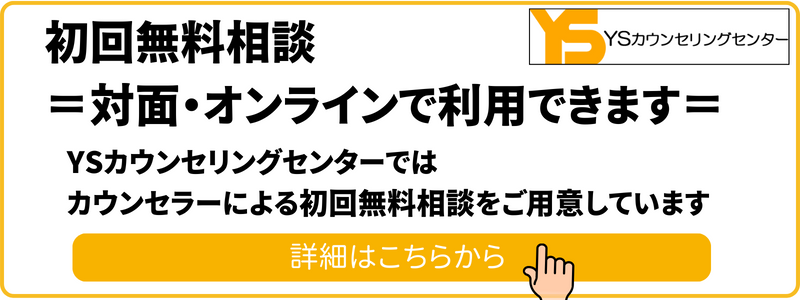
当センターでは、親御さん・ご家族の無料相談を受け付けています
また、「心病むお子さんを救う接し方講座」(無料)も月に1度開催しています。
ぜひお気軽にご参加ください。
「このままひきこもりになってしまうのでは…」
「不登校の子どもにどうやって接したらいいの」
という親御さんの無料相談を受け付けています。
子どもをよみがえらせるのは、医者でも、薬でも、相談員でもありません。お子さんの回復のカギは、親御さんの「接し方」にあります。ご家庭でのお子さんの様子や親御さんのお悩みなど、じっくりマンツーマンでヒアリングを行い、解決までの道すじを、具体的にご相談いただけます。
経験豊富なカウンセラーが対応いたしますので、少しでも気になる方はお気軽にご連絡ください。
↓ ↓ ↓
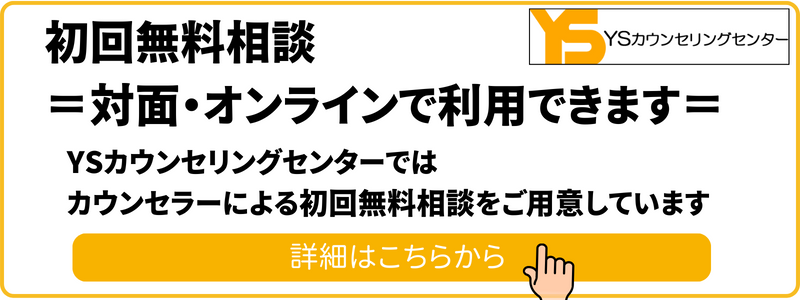
当センターでは、親御さん・ご家族の無料相談を受け付けています
また、「心病むお子さんを救う接し方講座」(無料)も月に1度開催しています。
ぜひお気軽にご参加ください。